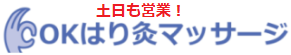月経困難症とは
月経困難症は、下記のような症状が月経直前ないし月経時におこります。
- 下腹部痛
- 腰痛
- 腹部膨満
- 悪心
- 嘔吐
- 頭痛
- 下痢
- 脱力感
- 食欲不振
- イライラ
これらの種々の症状を随伴する病的状態で、日常生活に支障をきたすほど強い症状を、月経困難症と呼びます。
月経痛(生理痛)とは、月経期間中に月経に随伴して起こる下腹痛、腰痛をいいますが、一般的には、月経痛と月経困難症は、同じ意味で用いられることが多いです。
月経困難症は、器質的月経困難症(続発性月経困難症)と機能性月経困難症(原発性月経困難症)とに分類されます。
器質的月経困難症は、骨盤内に器質的な原因(例えば、子宮内膜症や、子宮腺筋症、子宮筋腫など)があり、これにより月経困難をきたすものです。
これに対し、機能性困難症は、骨盤内に器質的な原因がないのに、月経困難症をきたすものです。
月経困難症はなぜ起こる
機能性月経困難症がなぜ起こるのかについては、様々な説がありますが、一番有力視されているのが、プロスタグランジン説です。
プロスタグランジン説とは、黄体期から月経期にかけて、子宮内膜で産生されたプロスタグランジンという発痛物質によって、子宮筋が過剰に収縮し、子宮内圧が亢進するため子宮筋が虚血性変化を起こすことにより、痛みを引き起こすとする説です。
また、月経時にみられる悪心・嘔吐・下痢・頭痛・疲れやすさなどの随伴症状も、プロスタグランジンが血流にのって、体中をめぐるためと考えられています。
機能性月経困難症の女性では、無症状の女性に比べて、黄体期から月経期にかけてのプロスタグランジンの産生が多く、子宮内膜及び月経血中のプロスタグランジンの濃度が高いと言われています。
機能性月経困難症に対する鍼灸治療
鍼灸刺激により、筋緊張が緩和させることで、症状を緩和させます。
また、鍼灸の作用で子宮血流を増やすと、増加したプロスタグランジンが洗い流されて子宮収縮を抑制し、症状を緩和させます
持続的な筋緊張は、血管を圧迫し、血流の悪化を招き、首のこり、肩のこり、頭痛、腰痛、冷え症など、様々な症状を引き起こします。
体の外側の筋が緊張していると、神経反射により、内蔵器の筋も緊張します。
子宮筋も例外ではありません。
1~2週間に1回の定期的な鍼灸治療を継続することで、交感神経の興奮の抑制を介して、筋緊張が緩和した状態を維持しやすくなります。
こうしたメカニズムにより、定期的な鍼灸治療の継続により、子宮筋をはじめとした全身の筋の緊張緩和が維持されることで、機能性月経困難症を改善・予防することができます。