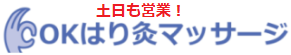月経前症候群(PMS)とは
月経前症候群(PMS)とは、月経前3~10日間の黄体期の間に続く精神的あるいは、身体的症状で、月経発来とともに減退ないし消失するものと定義されています。
月経周期を有する女性の40%程度に、月経前にイライラ等の何らかの症状が出現するといわれています。
そのうち、症状が周期的に出現し、日常生活に支障をきたす程度のものを、月経前症候群(PMS)といいます。
月経前症候群(PMS)の症状
身体的症状
むくみ、腹部膨満感、乳房緊満感(乳房痛)、体重増加、頭痛、腹痛、腰背部痛、筋肉痛、関節痛、胃腸症状、めまい、倦怠感
精神的症状
イライラ感、おこりやすい、抑うつ、涙もろい、不安、情緒不安定、集中力の低下、物忘れ、疲れやすい、眠気、引きこもり、など
この他、様々な症状がおこり、その症状の数は、150~300とも言われています。
月経症候群(PMS)はなぜ起こる?
月経前症候群(PMS)の原因は、今のところ、はっきりしておらず、様々な説がありますが、その中で特に有力視されているのが、「内因性オピオイド説」と「セロトニン説」です。
内因性オピオイド説とは
内因性オピオイド説とは、オピオイドペプチドのひとつである、β-エンドロフィンが過剰に分泌されることにより、血中LH(黄体化ホルモン)、プロスタグランジン、ドーパミンなどが低下し、プロラクチンが上昇、アルドステロンの分泌亢進などが引き起こされ、その結果、消化器症状・精神症状・むくみ・乳房痛など、多彩な症状が出るとされる説です。
セロトニン説とは
黄体期に脳内セロトニンが減少することにより、様々な症状があらわれるという説です。
エストロゲンは、セロトニンの日内変動を増加させ、プロゲステロンは、セロトニンの代謝を促進させるともいわれています。
女性ホルモンであるエストロゲン・プロゲステロンと、脳内神経伝達物質であるセロトニンが影響を及ぼしあい、様々な症状を引き起こしていると考えることができます。
月経前症候群(PMS)に対する鍼灸治療
PMSには、鍼灸がおすすめです。
鍼灸には、以下のような作用があります。
- 鍼灸刺激は、視床下部―下垂体―卵巣 のホルモン動態を調整します。
- 鍼灸刺激は、ホルモン分泌の中枢であり、自律神経の中枢である視床下部機能の変調を調整します。
体表への鍼灸刺激は、体制神経(感覚神経)を介して、中枢(脳)に伝えられます。その刺激が中枢(脳)自体の血流調整などを介し、中枢(脳)自体の機能を改善します。
以上のようなメカニズムで、1~2週間に1回の定期的な鍼灸治療で、月経前症候群(PMS)の様々なつらい症状を、徐々に緩和していくことができます。
もちろん、鍼灸治療だけの単独治療でなく、一般医療機関の治療との併用も可能です。
一般医療機関の治療の基本は薬物療法ですが、鍼灸治療と併用して問題がある場合はほとんどなく、むしろ、お薬の吸収を促進し、併用することによる相乗効果で症状の改善を目指すことが可能です。